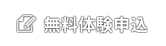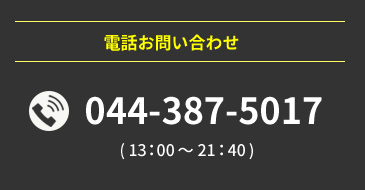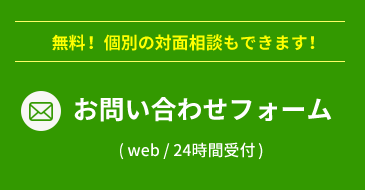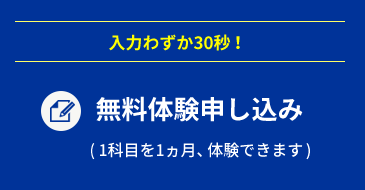2024.07.1
大学受験の入試方法・総合型選抜とは?
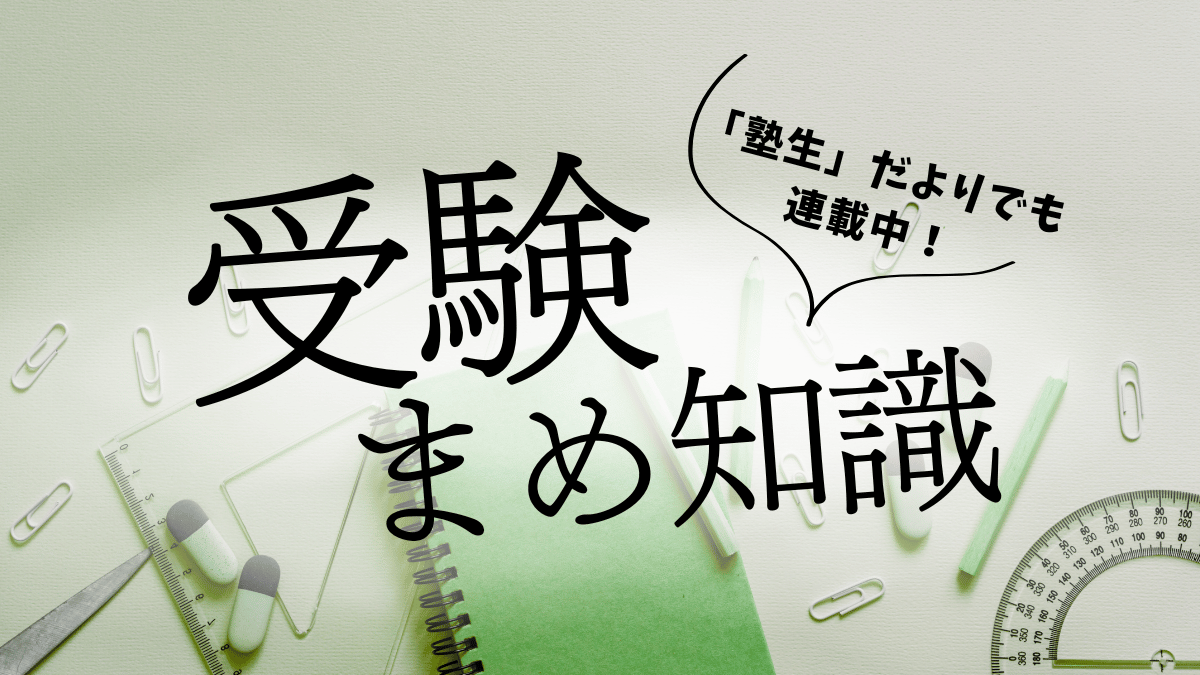
【1】受験まめ知識…総合型選抜(AO入試)とは?
入試にはさまざまな形態のものがありますが、一般選抜や学校推薦型選抜(推薦入試)と異なる「総合型選抜(AO入試)」という選考方法があります。
今回は、総合型選抜についてご紹介します。
◆総合型選抜とは?
総合型選抜とは、エントリーシートなどの受験生からの提出書類のほか、面接や論文、プレゼンテーションなどを課し、受験生の能力・適性や学習に対する意欲などを時間をかけて総合的
に評価する入試方式です。
従来の入試方式と比べると、「高い学習意欲」「学びへの明確な目的意識」が選抜基準として重んじられているため、選抜方法もその点が判断できるような内容となっています。出願時に受験生自身が作成して提出する書類が多いことも特徴です。
また、共通テストを含む教科・科目に係るテストや小論文、プレゼンテーションなど、学力を確認する評価方法を活用することが必須となっています。
◆総合型選抜のおもなパターン
◎選抜型
国公立大学や難関大学に多いパターン。小論文やレポートを課したり、長文の志望理由書や自己推薦書などを課してその内容をもとに面接するなど、大きな負担がかかります。
◎対話型
私立大学に多いパターン。エントリーや正式出願を通して複数回の面談・面接を行い、学力面より人物評価や意欲、志望動機などを重視します。
◎実技・体験型
入試プログラムの中に、模擬授業やセミナー、実験などが含まれ、その参加が出願条件となります。それにともない、レポート・課題提出などを行います。
このように、総合型選抜は一般選抜や学校推薦型選抜と比べて時間をかけた選抜方法で実施するため、受験に際する労力も相当なものになります。
また、出願時に提出するものも多岐にわたり、他の選抜方法に比べ、事前準備により多くの時間を割く必要があります。
受験を考える人は、自分の進路・適性をしっかりと考えた上で、早い時期から対策をしていきましょう。
【2】学校推薦型選抜(推薦入試)とは?
◆学校推薦型選抜とは?
「学校推薦型選抜」は一般選抜に次ぐ規模の選抜方式で、一般選抜との一番大きな違いは「出身高校長の推薦を受けないと出願できない」という点です。
出願にあたっては、「調査書の学習成績の状況4.0以上」といった出願条件が設定されている場合もあり、誰もが出願できるわけではありません。
学校推薦型選抜は、さまざまなタイプの選抜がありますが、大きく分けて「公募制」と「指定校制」の2 タイプに分かれます。「公募制」は、大学の出願条件をクリアし、出身高校長の推薦が
あれば受験できる選抜です。
一方の「指定校制」は大学が指定した高校の生徒を対象とする選抜ですが、私立大学が中心となっており、国公立大学ではほとんど行われていません。
また、一般選抜とは違い多くの大学では、「出願者は、合格した場合は必ず入学する者に限る」専願制の入試となっています(近年、他大学との併願が可能な併願制も増えてきています)。
学校推薦型選抜を考える場合は、出願するうえで制約があることと、原則第1志望校に限った入試であることを理解しておきましょう。
◆国公立大学の学校推薦型選抜
国公立大学の学校推薦型選抜は、私立大学に比べて募集人員が少なく、出願条件のうち「学習成績の状況4.0以上」など厳しい成績基準を設けている大学があるほか、高校からの推薦人数が制限される場合は、出願前に学内で選抜が行われるケースも少なくありません。また、共通テストを課す場合と課さない場合の2 タイプに大別され、その入試日程も大きく異なります。
大学での試験はさまざまですが、小論文など受験者自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方法のほか、プレゼンテーション、口頭試問、実技、教科・科目に係るテスト、資格・検定試
験の成績、共通テストなど、学力を確認する評価を実施することが必須とされています。
すでに「面接」「小論文」を課す大学は多く、口頭試問を含んだ面接や学科に関連した専門的知識を要する小論文が課されることも珍しくありません。
◆私立大学の学校推薦型選抜
私立大学の学校推薦型選抜は、入学者比率が40%以上を占めており、一般選抜と並ぶ私立大学入試の大きな柱といえます。
私立大学の出願要件は国公立大学ほど厳しくなく、なかには成績基準を設けない大学もあります。選抜方法は、小論文や適性検査、面接、基礎学力試験、調査書等の書類審査をさまざまに組み合わせて選考されています。近年は適性検査や基礎学力検査といった名目で学力を測る試験が行われている大学も目立っています。
◆注意点・対策方法
万一、学校推薦型選抜で不合格だった場合、その時点から一般選抜の準備を始めていたのでは間に合いません。学校推薦型選抜を考える場合は、早めに担任の先生や保護者とよく相談しましょう。
【Kei-Net 特派員の声…苦手科目の克服法】
現役大学生の「Kei-Net 特派員」へのアンケート結果から、特派員のナマの声をお伝えします。
Kei-Net ホームページにも、たくさんの「声」を掲載していますので、ぜひ覗いてみてくださいね。
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
【Q】苦手科目をどのように克服しましたか。克服法を教えてください。
▼すず特派員(横浜市立大 国際商 国際商 1年)
(日本史)
11 月になって日本史の基礎が抜けていることに気づき、思い切って通史を縄文時代から復習しました。通史を1周しか復習しない代わりに知識は全て吸収しようと心がけました。問題を解いて参考書を読むということを全ての時代において繰り返しました。12 月の中旬には日本史の流れがほぼ完璧にわかるようになり、共通テストでも8割得点することができました。
▼いちごドーナツ特派員(慶應義塾大 薬 薬 1年)
(英語)
まず、なぜ苦手なのか、点数が取れない原因を洗い出し、分野を絞って対策しました。私の場合は苦手な文法を復習した後、毎日長文に触れることで苦手意識を減らしていきました。苦手教科も、毎日触れると少しずつ感覚が慣れていくと思います。
▼M.T.特派員(東京医科歯科大 歯 歯 1年)
(物理)
基本を完全に理解し、自分の言葉で現象を説明できるまで教科書を読みました。教科書の内容を理解していないのに問題演習ができるわけがないので、周りが演習をしていても教科書を読み続けるメンタルが大事です!
▼M.I.特派員(東京慈恵会医科大 医 医 1年)
(数学)
数III は典型的な問題を解けるようにした。一つの問題集をしっかり解けるようになるまで何度も繰り返して解き直すのが、1番効率良く力が身につくと思う。
▼塩こうじ特派員(早稲田大 文化構想 1年)
(古文)
塾の授業を受けた後、授業内容を再現できるくらい復習の密度と質を高くした。教わっている先生を信じて、授業の内容を自分の中に落とし込めれば本番も解けるというマインドでいた。
▼コンクラーヴェ特派員(北里大 未来工 データサイエンス 1年)
(英語)
単語は単語帳やアプリを使ってスキマ時間に活用。英文解釈は夏休みに重点的に。長文読解は1年を通じて講座で力をつけた。バランスよく多分野を効率的に学習して対策した。
▼カイ特派員(愛知教育大 教育 1年)
(数学)
同じ問題集に繰り返し取り組むことが大切だと思います。複数回取り組むことで理解が深まり、類似問題への対応力がつきます。また、いくら苦手でも何度も繰り返していれば、解法を覚えて
いつかは解けるようになります。その際の達成感を自信に変えることで、克服することができるはずです。
▼T.M.特派員(立命館大 法 法 1年)
(理科基礎)
基礎本を何度も読み込む。その後、共通テスト形式の問題を何回も解いて、間違えたところをノートにまとめた。実際に共通テスト本番には、その「まとめノート」の内容が複数問出題されたので、本当にやってよかったと思っている。
▼S.F.特派員(龍谷大 心理 心理 1年)
(国語)
国語だけ塾の講習に行きました。国語の場合、解き方のコツが理解できれば、あとは何度も解いて慣れていくことが最重要であると感じたので、夏休み明けから必ず1日1題以上現代文の読解問題を解くようにしていました。
古文は単語を理解したうえで文章に慣れるよう、現代文と同様、何度も問題を解いていました。
▼長州の麒麟児特派員(山口大 国際総合科学 1年)
(数学)
基礎・基本はできることは分かっていたので、応用問題にひたむきに取り組んでいました。たとえば、二次関数の基本的な計算問題はできていましたが、文字が含まれる大小問題は苦手だったので、徹底的に対策をしました。
【勇気の出ることば…受験生に贈る珠玉の名言】
大学受験に挑むあなたに、勇気の出ることばを贈ります
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing.
Abraham Lincoln (16th President of the United States)(訳)いつでも、肝に銘じていなさい。あなた自身が持つ成功への決意が何よりも重要だという
ことを。
(エイブラハム・リンカーン 第16代アメリカ合衆国大統領)
私たちにとって敵とは、「ためらい」です。自分でこんな人間だと思ってしまえば、それだけの人間にしかなれないのです。
ヘレン・ケラー(アメリカ・教育家、社会福祉事業家)