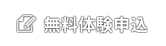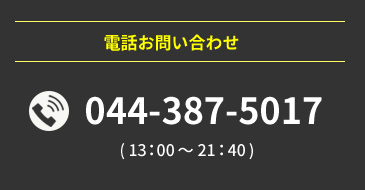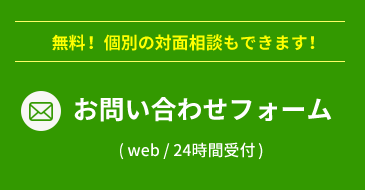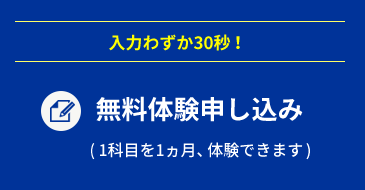2024.08.6
模試を受ける目的
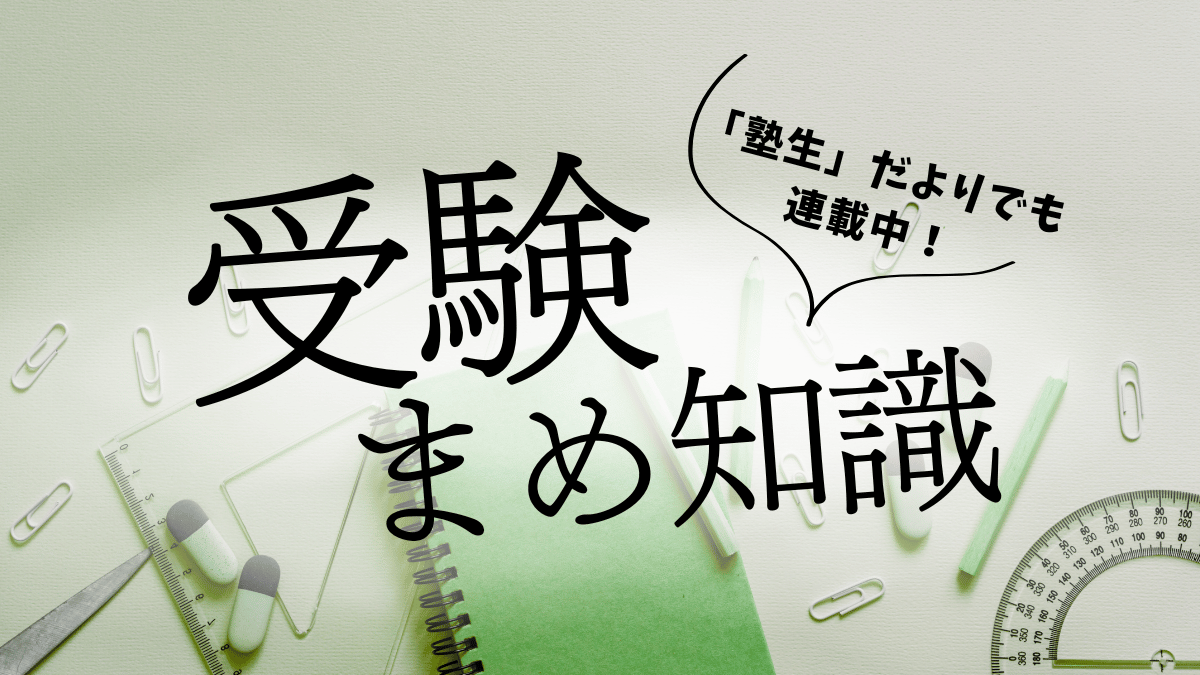
受験生のみなさんは、学校や塾を通して模試を受験する機会があると思います。でも、「みんなが受けるから」「学校で受けろと言われたから」という消極的な理由で受験している人はいませんか?そこで今回は「模試を受ける目的」について考えてみます。漠然と受験するのではなく、以下のポイントを押さえて受験しましょう。
◆弱点科目や分野を把握する
自分の学習がどこまで進んでいるのか、まだよく理解できていないところはどこなのか、どこでつまずきやすいのかなど、模試を通して自分自身を客観的に見てみましょう。
復習が必要な分野、重点的に学習すべき分野などを教科ごとにリストにまとめておくとよいでしょう。
◆志望大学合格までの距離を測る
模試には、志望大学合格までどのくらいの距離があるのかを測る、という目的もあります。ただし、偏差値や合格可能性評価ばかりに目がいってしまうのは考えものです。この評価はあくまでも「模試を受験した時点での目安」でしかありません。
模試では常にA判定をとっていても、実際の入試では思うように力が出せないこともありますし、逆に模試ではなかなかよい判定がとれなくても、それを糧にして見事本番では合格する、という例もたくさんあります。
評価が良かったからと安心せず、また悪かったからとすぐに諦めたりせず、目標に向かって頑張りましょう。
◆高3生・高卒生にとっては入試本番の予行演習に
入試は学校の定期考査とは雰囲気も試験時間も違います。実際の入試で自分の実力が十分発揮できるように、時間配分などにも気を配り、入試本番の予行演習として模試を受けましょう。共通テスト対策模試の場合、あとで自己採点できるように、自分の解答を問題冊子にメモするのを忘れずに。
◆模試を受ける心構えや気をつけたいこと
以上のことを踏まえ、模試を受けるにあたっての心構えや、模試の受験時に気をつけたいことなど、模試をとことん活用するためのチェックポイントをわかりやすくまとめて、Kei-Net に掲載しています。しっかり確認して、ひとつひとつの模試を有意義なものにしてください。
◆河合塾の全統模試は自宅でも受験できる
河合塾が実施する全統模試の中には、個人でお申し込みの方(一般生)を対象にした「自宅で受験できるサービス」を行っているものもあります。公開会場が近くにないときなどにご活用ください。
【Kei-Net 特派員の声…マーク式模試の活用法】
現役大学生の「Kei-Net 特派員」へのアンケート結果から、特派員のナマの声をお伝えします。
Kei-Net ホームページにも、たくさんの「声」を掲載していますので、ぜひ覗いてみてくださいね。
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです
https://www.keinet.ne.jp/toku/advice/
【Q】マーク式模試をどのように活用したか教えてください。
▼うめめ特派員(学習院大 文 1年)
間違えた問題は必ず間違えた理由を書き出して、次にどのように気をつけるかの自己分析を受験直後にしました。2回目は成績返却後で、何も見ずに全て解き、間違えたらまた自己分析をします。最後は長期休みで、間違えた問題のみ、やり直しました。間違えた問題は自分で解説できるまでやり込みました。
▼いちごドーナツ特派員(慶應義塾大 薬 薬 1年)
なぜその問題で点を落としてしまったのか考えました。時間制限がなければ解けたのか、単純に内容の理解が足りていなかったのか、分析しましょう。時間が足りないのなら予想問題などで練
習し、内容の理解が足りないのなら教科書を読み直す、というようにして復習していました。
▼T.M.特派員(立命館大 法 法 1年)
理科と社会は、自分が間違えた問題やたまたま正解した問題で、知識が不足していたところを「復習ノート」を作成してまとめていた。共通テスト本番前に何度も見返した。共通テストにも、復習ノートに書いていたことが出題されたのでやってよかったと思っている。
▼はる特派員(岡山大 医 医 1年)
間違えた問題が、わからなかったのか、ひっかけに嵌ったのか、マークミスなのかをまず選別しました。分からなかった問題はその分野を勉強し直して、ひっかけだった場合は何に気づかなかったのかよく分析しました。
▼S.I.特派員(九州大 教育 1年)
目標点数と自己採点の点数を比べて、どうすれば目標点数に届いたのか、逆にどうして目標点数以上の点数をとれたのかを分析しました。そうすることで、次の模試では何を意識して解けばいいのかを明確にすることができ、成績の向上につながりました。
【勇気の出ることば…受験生に贈る珠玉の名言】
大学受験に挑むあなたに、勇気の出ることばを贈ります。
今日できないようなら、明日もだめです。
一日だって無駄に過ごしてはいけません。
ゲーテ(ドイツ・詩人)